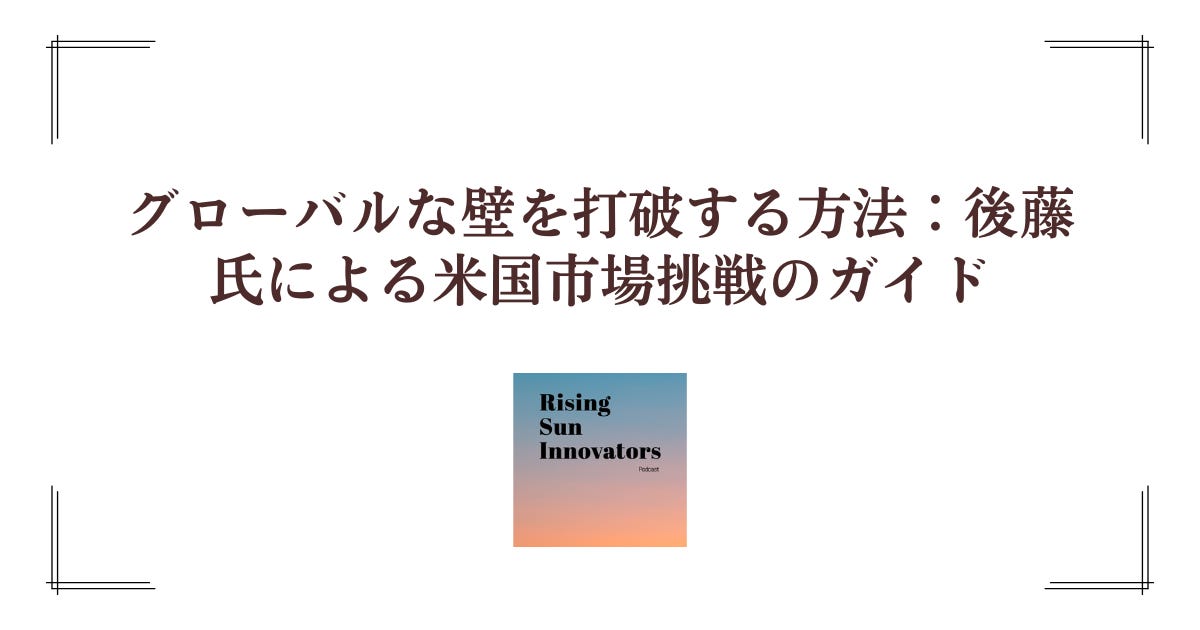本記事では、後藤氏がスタートアップのグローバル展開、特に米国市場での挑戦について掘り下げています。後藤氏は、国際的な成功に向けた実践的なアドバイスと経験を共有し、直接市場を体験する重要性を強調しています。文化的・運営的な障害を克服するための適応力が不可欠であることを伝えています。
注目すべき内容:
実体験の重要性: 後藤氏は、ターゲット市場を直接体験することが成功にとって重要だと強調しています。初回の訪問で新しい国での運営の現実を知り、繰り返しの努力で市場をよりよく理解し適応することができると述べています。
文化の違いと適応: 日本と米国の間の文化的なギャップ、例えばコミュニケーションスタイルやビジネス慣行の違いについて指摘しています。これらの違いを理解することが、効果的な対話や交渉のために必要不可欠です。
日本の起業家が直面する課題: 多くの日本のスタートアップが、米国での資金調達やチーム作りの難しさに苦しんでいます。後藤氏は、これらの課題がしばしば起業家に再考を促し、日本に戻る原因となることが多いと述べています。
Tech Houseの役割: Tech Houseは、日本の起業家が米国での挑戦に対処するためのコミュニティとリソースを提供するシェアハウスであり、そのサポートネットワークの重要性を後藤氏は強調しています。
— 後半も始まりました 後藤さん、改めて よろしくお願いします 前半の動画では、 後藤さんのバックグラウンドを 今やってるスタートアップ立ち上げた きっかけについて 色々触れさせていただきました 前半の動画を 見てない方はぜひ前半の動画も チェックしてください 後半では グローバルっていうキーワードを 念頭に入れながら 質問したいと思いますので、 よろしくお願いいたします。
後藤さん「はい、よろしくお願いします」
—よろしくお願いします 前半の動画 でもちょっと色々と 海外での チャレンジ する時に考えてた... 課題だったり とか、恐らく 後藤さんなりのアプローチっていうのは 色々と軽く言っていたと思うんですけども、 おそらく日本でも 海外にチャレンジしたいけど、でも どうしたらいいか分からないっていう方々って たくさんあると思う... たくさんいると思うんですよね もし海外でチャレンジするには、 もちろんその後藤さんとか、 その経験を踏まえて ですね、どうするのがいいのか っていうところで 質問したいんですけども どうしたらもう海外に チャレンジしたいけど、そこに一歩踏み出せるには どうしたらいいんですかね。
後藤さん「そうですね でももうすごい シンプルな話としては、やっぱり来ないと 難しいなとは思いました で、さらに言うと、 僕もそうだったんですけど、最初は 3ヶ月、僕も去年 3月から6月にかけていたんですけど、 回目は正直 そんなにガッツリ進捗作れたかって言ったら そうでもなくて、一番何か ようやく現地で うまくやり始めたなっていうのが 2回目だったんですね 要は、まあ 12月で すごく 僕もテックハウスっていう、 アメリカに来たい人の シェアハウスみたいなところに 住んでた 今も住んでるんですけど 住んでたんですけど、すごい 日本から来られる方 去年は大体人ぐらいいらっしゃったんですね そこに来て ただ ただ、一回来て、 その後回目来た人っていうのが ほぼいなかった 僕を含めて、 2~3人ぐらいだったと思うんですよね 大体その本当に 回目来て、USって こんな感じかってなった時に、 大体みんなどこかで 多分苦労を感じるんですよ それはその 資金なのか、メンバー集めなのか、 クライアント探しなのか、何かしら 人モノ金みたいな課題を感じて、 そうなった時に、当然なんですけど、 スタートアップやってるからには 何か事業を成立させなきゃいけないって 発想になると思うんですね で、 USでやっていくハードルって、そう、 何て言うんすかね、日本よりかは 高いわけじゃないですか そうなってくると、 現実的に何かこう 成功させるって考えた時に、じゃあまずはこれ 日本からやっていこうってなるわけですよ で、 そこは 何て言うんですかね、ハードルになるので、まずは 何か一回来てみて 活動するのがいいと思うんですけど、 それもやっぱ、USで 何かやっていこうってなった時には ちょっと考えなきゃいけない 要は 単純にその、なんか 日本のユーザーだけを最初ターゲットにして、 日本からだけ採用しよう、 日本でだけ しよう っていうふうになると、多分 もうUSで展開するって 結構遠のいちゃうかなって思うんで なんかうまくやらないといけないんじゃないかな っていうのが、 多分みんな直面する 最初のハードルだと思います。」
—なるほど じゃあまずそれがUSなのか どこなのか 一旦置いといて、まず 行ってみるっていうのが結構 大事っていうことですね もう自分の目で 見て感じて、判断して、で、行ってみて、 そのマーケットに可能性を感じるか 感じないかを見極めるっていう感じが 一番良いって感じなんですかね まず行ってみる。
後藤さん「そうですね 結局スタートアップでも、じゃあ 採用していくとか、調達していくとかっていうのも 何かはやってみて 失敗して試行錯誤して そこに最適化するってプロセスが 絶対入ると思うんですね それを USの対象に向けて やっていかないと、 何かそこに進出していく力っていうのは 絶対に身につかないし、じゃあそれを 日本で最適化していったら 持っていくのは難しいわけですよ それこそ例えばすごい シンプルな話ですけど、資金調達の仕方とかって 日本とUSで全然違うわけですよね そのピッチの構成とか、どういうストーリーが 評価されるかって全然違ってきます さっきの話でも 日本 USだと、 そうじゃないかもしれないわけですよね だからこっちに来て 失敗して、じゃあその失敗を どうやったら乗り越えられるかっていう、 そのフェーズまで行けるぐらいは 最低限継続して 挑戦しなきゃいけないはずで なのでそれってまずこっち来ないと そもそもその人たちは話せないと思うし、 それじゃあ、一回話して失敗した後に じゃあどうやったら 自分の持っているリソースとか スキルでそれを獲得できるのか っていうのを考えて試す そこまで行かないと海外での 最初の一歩までいかない なので 来るのは前提で来て、後に、 もう来た後に、ヶ月じゃ上手く行かない前提で なんかこう考えていくぐらいでないと どこかで多分心折れちゃうんじゃないかな っていうのは強く思いました。」
—ありがとうございます確かにそれはそうだなまず期間決めてやってみて、ダメならまた別のアプローチを考えて、その試行錯誤をとにかく繰り返して、その失敗から学んでいくっていう感じですね学んで成長していくっていうのが結構大事ってことですね。
後藤さん「そうですねそれができる期間を確保しないと、やっぱり結構、例えば日本だったら投資家とかも、話って基本、聞いてくれるわけじゃないですかこれは投資家に限らず、日本人ってちゃんとミーティングして話を聞いてくれる度合いがすごく高いと思うんですよねお互い、相手にリスペクトがあるとか...でもUSってそんなことないので話聞いてないですし、話しようと思ったら、じゃあリファラルがないといけないしとかってなってくるそうすると僕が思うんですけど、日本人が心折れるタイミングってなんか相手が失礼とか、そういう相手の態度で何かこう、自分がこう丁寧に扱ってくれないことに対して、何かこうカルチャーギャップを感じて日本に戻っていくっていうことが僕は多い気がしてるんですよねだから会話の中で相手が失礼だみたいなことを、まあこれは分からないですけど、僕もアメリカ人じゃないんで、わかんないですけど、日本人はこれ言いがちだなって思うんですけど、なんか、アメリカでそういう話をバッドレピュテーションで聞いたことがあんまり...ない...よっぽど態度が悪い場合は別だと思うんですけど、相手に丁寧に扱われないと、何か気落ちしちゃうみたいなことが日本人って多いのかなとかは思いつつ…」
—それは確かに カルチャーギャップとして もしかしたらあるかもしれないですね それはね ちょっと分かんないですけど なんか、
後藤さん「そういう、少なくとも何かそういうところでトラブったみたいな話を日本人とUSの人がトラブったみたいな話をちょこちょこ聞くので、それで(そういったことが)あるんだろうなとは思った。」
—なるほど あと多分やっぱり 私も結構米国に行ったり 来たりすることもあるので、恐らく そのコミュニケーションの コンテキストの中で、 やっぱり日本人が結構 キツイと感じるかもなって思う瞬間は、 やっぱり英語って ストレートじゃないですか イエスかノーって 物事がはっきりしてるので なので 日本語って結構 曖昧な表現が多いのかなってちょっと思って 例えばやっぱり日本人同士だと やっぱリスペクトを持って 接していく中で、 どうしても色々なことを 曖昧にして、こう 相手の気持ちを 害しないようにって 多分工夫はすると思うんですけども、英語とか 一言で言うと、米国の方とかもそうなんですけど、割と ストレートフォワードじゃないですか 言うことが なので曖昧なことも言わないし、別に 向こうは悪気があって 否定的なことを言ってる 言ってても、そこは悪気はなく、 多分恐らくもうストレートに 自分の考えていることを 主張しているだけなんで、 ちょっとそこら辺のギャップも 確かにあるかもしれないなとは思いますね はい...なるほどな 確かにそれはそうかもなってちょっと考えさせられました ちなみに視聴者の方々が 恐らく分からないと思いますので、 簡単でいいので、このテックハウスって どういうところなんですか?
後藤さん「そうですね、テックハウスっていうのは 元々は 今Anyplaceっていうスタートアップをやられている 内藤聡さんという方がいるんですけど、 その方がUSで ちょっと今閉じちゃったんですけど、 Ramen Heroっていう 日本のラーメンをUSに持っていくっていう スタートアップがあって その方と人で始めたシェアハウスみたいなのが起源で で、それが いろいろ代替わりをしていってるんですけども、 いわゆるUSで挑戦したい人達が溜まって 活動していくっていう 一種のコミュニティみたいな形としてあるんですけど、 それに、僕がいた いたし、今もいるっていう話です。」
—という感じですね なるほど ありがとうございます じゃあもうみんな、 例えばスタートアップが ちょっと米国で行きたい、だけどツテがないってなったら テックハウスを利用すれば、それが もうそこの課題は クリアできるって感じですね。
後藤さん「そうですね 今本当に 結構場所自体も すごくいいところにはあって、結構 本気でやりたい人がいたら、 ちょっとコンタクトしてみるといいかもしれないです 場所自体は結構今そうですね すごいこう、なんだろう、コミュニティーとして すごく純度を上げていこうっていう 感じになっているので、 ハードルは結構上がってはきてはいるんですけど、 それでも本気でやりたい人いたら、 そういう人は全力でサポートしていく場所 だろうなと思っているので、 コンタクトしてみると良いかなと思います。」
—わかりました。ちょっとこの、この動画もいろいろ書き起こしていますが、その記事でも書いていく、書いていくのと、あと概要にもテックハウスの情報を入れておきたいと思うので、皆さん、もしテックハウスに興味があったら、そこにアクセスしていただければなと思います先ほどテックハウスに訪れる方が去年とかでは人くらいいて、だけど一人も戻ってこなかったというか...後藤さんを除いてだと思うんですけども、それって何でなんですかね要は行ったっていうアクションは起こせたわけじゃないですかなんでなんだろうなというふうに思うのと、あと、どういう方々が訪問というか、行くんですか?ペルソナでいうと。
後藤さん「これはいくつかまずパターンあると思っていて、 パターンあるんですよね 一つが、要はこれから スタートアップをやりたいってなった時に そうですね USも 一応候補として 検討しておきたいなと それで来るパターンの一つですね もう一つは、今既に日本で 事業をやっていて、USは 次の...要はなんですかね... 凄くアップサイドに... マーケット拡大っていうところですね まで行きたいっていうパターンですね 割合的にはどうですかね まあ9対1か8対2くらい 2の方が既にやっている方ですね っていう感じにはなるんですけど、 これは大体パターン化されてると思っていて、 まず一番最初の方々に関しては、 僕もその中に含まれるんですけど、 やっぱりどこかで何かこう...ハードルを感じて、 大体マックスで来れても3ヶ月じゃないですか それで日本戻るんですよね、 そうした時にもう一回行こうってなりづらいんですよね これは色々あると思います もちろん、例えば そもそもスタートアップって リスキーなものじゃないですか 日本で考えた時に、こっちでスタートアップやろうと で、その中で アメリカでやっていると、 ただでさえ難しいスタートアップが もっと難しくなるわけですよ 日本ってスタートアップやるのめちゃめちゃレアで リスキーだけど USと比べたら、僕目線で言えば圧倒的に 難易度低いなって思うんですよ そもそも日本だったら 投資家と会話がちゃんとできるし みたいな...例えばですけど。 こっちだとある種リファラルだったりとか、 1種の何ですかね... そういういい話に辿り着くためにすら競争があって、 そういう競争に細かく選抜されていかないと、 ちゃんとしたステージに立てないと、 当然、USだったらスタンフォードとか そういう人とかは最初からいい扱いです でも 移民でバックグラウンドなくて、なんなら 英語もちょっとパーフェクトでないと なった時には、まず中で目立つ ところで競争していかないといけない で、どこかで 当然期待を感じるわけですね そうなった時に、 なんでこの わざわざこんな競争に 今立ち向かっているんだろうと ただでさえスタートアップ難しいのに そこでやり続けるのが 正解なんだろうかって なるんですよ 大体が なったらじゃあ 日本で最初は チームは採用しようとか、チームなのか メンバーだけじゃなくて、 そのユーザーは最初日本にしようなのか、 そういう風に リソース集めを じゃあ日本でやっていこうってなるわけですよね で 一回日本に戻って、リソース集めを そっちでやってたら、じゃあもう一回 また来てやろうってなった時に、 本当にこれ効果あるんだろうかって 疑いが出ると思うんですよ 日本でようやく立ち上げができ始めていて、 じゃあ、またこれ前回みたいに 戻っていって、やった時に 効果ないんじゃないか まず物価も高いし、コストもかかるし、 なんなら難易度も高い そこで踏ん切りつくのに、 何かすごい 重力がある印象があるんですね 僕も実際に回目に日本に戻って こっち来る時に ちょっと戻りづらかったですね 初めてUS行く時 じゃあこれから 新しいチャレンジだっていうので、ある種 非日常みたいな感じで行けると思うんですけど、 じゃあ、もう回戻ってきて 何かやっていこうってなった時に 前回の経験があって、前回、 しかもそこまでめちゃめちゃうまくいったわけじゃない なった時に、 じゃあ次に行ったら 何が変わるのかって 理屈で計算立てていくのは 非常に難しいはずなんです だから、そこで 合理性を考えた時に 戻ってこれないっていうのが 僕は一番でかいと思います。」
—なるほどじゃあそこに後藤さんはやっぱりそれでもやっぱチャレンジしようって思えたのってなんでなんですか?多分2回目で、多分その話を聞いてると確かに確かになって思うので、やっぱその中でもやっぱり後藤さんはもうやっぱ行こうって、やっぱり意思決定できたのってやっぱそこの何というか、背景って何なんだろうなっていうのはちょっと気になりますね。
後藤さん「そうですね やっぱりいくつか もちろんあるんですけど、 Gaudiyでグローバルチャレンジして っていうところもありますし、 それ以外にもGaudiyを退任した後に、 いくつかスタートアップを 一緒にお手伝いみたいに入ったりとかもしたんですね で、グローバルにチャレンジしたいな って想いがあったので なんですけど、やっぱり いろんなところが多いんですけど、 やっぱり現実的な理由を考えた時に どこかで妥協が入るんですね それは妥協って言い方をしたら悪いんですけど、 合理的に考えたら そこに入るべきじゃないよね っていう意思決定になる 点があるんですよ それはなんか... 会社を米国に移そうってことなのか、 メンバーを向こうで誘うってことなのか、 色々レイヤーはあるんですけど、 どこかで日本でやった方がいいよね ってなるんですよ でそこで何か その意思決定をしたら やっぱりやりきれないな っていうことを経験値で 思っていたので、 そこを今同じことをしたら 多分同じ結果になるなって 結果っていうとわかんないですけど、なので 行かなきゃいけないなっていう想いが あったので、なんとか 重い腰を上げてたと 後はテックハウスの方も やっぱり受け入れてくださったんで、 そういうコミュニティの支えもありつつ、 なんとか来れて、で 2回目が本当に僕は すごく良かったんですよね 2回目でちょっと 軽く会ってた人とかと もう一回会って話したりとかしてですね、何か そこで何か2回目とか 来るとちょっとこう現地とかでも 話しやすくなるんですよね 日本コミュニティもそうですし、そうじゃない海外って やっぱり短期的に来て帰る人って いっぱいいるんですよ サンフランシスコでは なので 継続してイベントとかやったりとかして あ、なんかこの人良くいるねとか っていうのがあって、初めて 何かを受け入れられる感じがあって そこまで受け入れられてくると ようやく物事が 進み始めるみたいな感じがあって 何かそれで基盤ができて、次は こっち戻りたいなっていう思いで、今 僕は3回目に来てるんですけど なので そこの初回と 2回目のハードルっていうのが すごい高いし、絶対に 回目だけは 夢を持って来れるんですけど、回目以降とかに 同じ考え方になるんですけど、絶対合理性の方が 上がってくるんで、だから そこを超えられるかどうかということかなと思うんですよ。」
—ありがとうございます ちなみに後藤さんは 英語のところとかは元々 何て言うか、やっぱ多分 エンジニアのバックグラウンドとかもあるし、 恐らく別にその言語 というか、別の言語を 習得するとか 勉強するっていうのは、 恐らくあまり 拒絶反応は あまりないとは 勝手に思ってはいるんです けども、元々は その英語というかはできていた 感じなんですか?
後藤さん「いや、全然できないですね 自慢じゃないんですけど、 僕も例えば高校の、 英語の偏差値とか 言うのであれば、一番最初、 多分高校年生の末頃ぐらいの偏差値 40ぐらいでしたし そうなんですか 1年勉強して、いわゆる 読み書きだけはできるように 読むとかは(出来るように)なって ただリスニングとかスピーキングは 全くできませんみたいな状態だったんですね で、そこからは 退任してから、大体半年ぐらいですかね 半年ぐらいひたすら 英語をやって、それでも そこでもそんなにレベルが上がってはなかったですね その時はTOEICやって、じゃ TOEIC点とかを3か月で取って みたいにやったんですけども、 全然聞けないし、喋れないですと だけど 年の11月に ハッカソンがあったんですね サンフランシスコで そこで審査員の人とかにめちゃめちゃ 喋らなきゃいけないとか、 デモ動画撮って出さなきゃいけないとかなって 現地で使わなくちゃいけない状況が出てきて、 そこで一気に何かできるようになりました で成長したって感じですね なので。」
—環境にいるとやっぱり使わないといけない、使わざるを得ない状況に追い込まないと、結局やっぱり使おうとしないし、喋らないし、やっぱり喋らないと身につかないし、というのはあるので、やっぱ一番前半の動画に戻りますけど、やっぱり行くっていうのが大事かもしれないですね。
後藤さん「そうですね 特に ファウンダーだったりとか、何か 自分の関連する事業がある 時は、事業の話を 英語でできるってのは 簡単だと思っていて 例えば、じゃあオンライン英会話教室とかで 写真を見て、写真の解説を英語でしてきたり、 そういうこととかってあったりするんですけど、 ああいうのは全然 僕も得意かと言われたら全然得意じゃないですけど、 事業の話はなんか 比較的簡単にできるじゃないですか めっちゃ考えてるし、なので何か そこで話して、意外と こういうことだったら話せるし 伝わるんだなってなってきて、ちょっと自信がついて、 それからは何か全然 そうですね 聞き取りとかも気づいたら できるようになってたし、喋れるようになってたし、 やっぱ耳が慣れてきますもんね 現地にいると聞くとね そうですね、未だに 全然聞き取れない 人はいるんですけど、ちょっと 訛り強い人とか、あとはすごい 何か流暢な 人って言うと変ですけども、 ネイティブの人がなぜこうすごい ボソボソと喋る時 あるんですけど、でも聞き直したら聞けるし、普通の 喋ってるのは全然聞き取れるんで、 確かにあと向こうになんだろう。」
—もうちょっとゆっくり話してくれるって言えば、やっぱりね、ゆっくり話してくれますしねきっとね。
後藤さん「そうですね まあ なので多分...話すとか 自体はそんなに問題はないと思っていて、例えば でも僕がちょっと今日 例えば大変だなと思ったのは、 今日は何か ちょっと変な話なんですけど、 今香港のアクセラに向かっていて、 そこの人と話してたんですけど コントラクトの ちょっと調整の会話をしてたんですね なので もうちょっと エンジェルで今はUSの弁護士がいて、その人と 向こうの担当者と 弁護士連れてコントラクトの項目の話を バーっとしたんですけど、こういう ちょっと大変な場面で キャッチアップして 適切に喋るとか、 そういうのはもちろん大変なんですけど、まあ そういうちょっと特殊な、 こういうちょっと ハードな場面とか、 じゃあイベント行った後に ちょっとクラブ行こうぜとか 誘われて、クラブで一緒に話して仲良くとか そういうのは大変です 大変なんですけど そのピッチするとか 採用するとか、 そういう型があるようなこととか、 あとチームメンバーって結局、内輪のことじゃないですか だから、何か別に、 聞き取れなかった時は 聞き直せばいい話だし、メッセージで意思疎通できるんで ミスできない場面で、かつ何かこう、 シチュエーションが難易度高いのは 大変ですけど、それ以外で苦労するってことは あんまりないんじゃないかなって 何か英語がハードルになって、その立ち上げが できないことは ないと思うんですよね。」
—なるほどね でも確かに そんな感じ 何か これはあくまでも 個人的な仮説なんですけど、 海外でチャレンジしたいけど 行けない、なかなか行けない 理由の一つは、 英語が完璧にできないからって 勝手にみんな思ってるからなのかな ってちょっと思って それが足かせになって 英語ができるようになって から行くわっていう感じで みんな考えてると思うんですけども またはそうじゃなくても 行く方が早いって 自分は思っていて だけど やっぱ喋れないと ダメだって 多分思ってるんじゃないかなと思うんですよね なので これをなんだろう リスナーの方が聞いたら、 それで何かいろいろとみんなも 何か勇気をもらえたら いいんじゃないかなと思っていてですね なので本当に 英語ももちろんできた方が ベストだけど、 でもマストじゃないよ っていう感じですね。
後藤さん「そうですね 何か 結局、例えば何だろうな 移民というか、 アメリカの外から来る人で、 その中で英語が得意じゃないとかって 前提があった中で、でも それでもどうやって 興味を持ってもらえるかとか 考えていたらいいと思うんですよね で、 僕のケースで言うと、本当に その採用だったりとか、もしくはその クライアント獲得とかっていうのは プロダクトのコンセプトで ほとんど取ってるんですよ それはなんか めちゃめちゃ...なんだろうな... コモディティー化してるものを うまくセールスしていってるとかではなくて、 誰もやってなくて でも こういうことを話したら 向こうから興味持ってくれて プロダクトとしても 面白そうな領域じゃないですか ゲームが 絡んでいて、 そこに取り組みたいっていう人は いるわけですけど、僕の場合は みんながやりたいことを 今やりたいけどあんまりやれていないことを 代わりに旗を立ててやっているから、向こうから 興味を持ってもらえる 何かそういう戦略って いくつかあると思っていて 例えば日本のファウンダーであれば、 日本文化を 持ち込んで、こっちで展開するスタートアップって 結構あると思うんですよ USでやってるのって、 お菓子とか、食べ物だったり... それも結局 その物自体に 興味を持ってもらえるし、提供できるのが 自分しかいないとか、強みが だからどうやって その環境だったり、今のスキルで やっていけるかって考えていったら なんとかなるし、じゃあそれ 英語とか何か補うものがあれば あんまりそこって気にならなくて、 何かむしろ何だろうな、 どうやって向こうで 人に興味を持ってもらうか っていうことを考える方が、英語より優先度 高いんじゃないかっていうのは。」
—なるほどね 確かにアメリカ の場合、移民も多いですし、完璧に 英語を話せる 人が全くいないんじゃないか なと思ってて というのも、いろんな人種がいる 中で、いろんな 訛りもあるし、ネイティブのアメリカ人でさえ、 いろんな州に行けば、別の州に行けば 別の訛りがあるし、なので 完璧な英語って何だろうって 考えたら、別にあまり 気にしなくていいんじゃないかなと思うのと、あと 自分の文法が間違ったら どうしようとか、発音とか間違ったら どうしようとか、本当に そういうのも気にしなくてよくて、 やっぱりもういろんな訛りがあるんで、 それも自分の個性として 割り切って話したら いいんじゃないかなとはやっぱ 聞いていて思いますし なので、自分の言葉で 話すからこそ、 やっぱりその人は 興味持ってもらえるようになるし、やっぱり 自分の言葉で とにかく話すっていうのが やっぱ大事なのかもなぁって 改めて思いましたね なるほど ありがとうございます ちなみに やっぱり海外という キーワードの中でも、いろんな マーケットが あると思うんですけども、 その中でもまあUSを選んだ 理由っていうのと、あとその 何て言うんですか、選定基準って どういうことを 考えてたんですか?
後藤さん「そうですね、理屈と感覚 ベースの話は別なんですけど、まず 感覚ベースな話で言うと、 海外でチャレンジしようとなった時に、 これは僕の本当に 勝手なイメージなんですけど、なんか 日本よりも 表現めっちゃ悪いんですけど、格が 低い国に行こうっていう 発想になることが 多いなって思ってるんですよ 勝手に 要は 英語も自信もないし でもその中で 評価してもらいやすいだろうなって思う まあこれは分かんないですか わかんないですけど だから アメリカになんかこう 行こうってなる ケースってのは、割合というのは 少ないんじゃないかなと思ってんですよ 海外 展開しようってなった時に ただ、結局、 じゃあ統計的な話で言った時に ですよ、マーケットのサイズだったりとか、いわゆる、 じゃあスタートアップのエコシステムの大きさ だったら、圧倒的に 一番大きいわけじゃないですか なので当然、じゃあ そこに対して 影響力を持っていくっていうことは、全世界に対して 意見を持つってことが強いと思うんですよ なので もうなんですかね、 当然僕のバックグラウンドだったりとか、 そういうことが自然と 評価されることは、USの場合、その内と 実際そうなんですけど、でも まあ、ここで成功するっていうことが 全世界に対して影響力を持つことが一つ 一番近いと思ったので、そういう意味で言うと アメリカ以外の選択肢なかったのかなっていう感じです。」
—なるほど、そっか確かにマーケット選定もおそらく大事なんじゃないかなとは思いますねあとはなんだろう、確かにそのマクロ的な要素で見た時に、アメリカはやっぱりそのスタートアップユニコーンの数で見ても、やっぱスタートアップエコシステムで見てみてもやっぱり一番なんだろう、出来上がってるって言うかっていうところももちろんあると思うんですけど、それ以外で言うと、やっぱり何か私、これも個人的な意見にはなるんですけど、ほんとにその国が好きかどうか、もうっていうのも結構大事になるんじゃないかなとは思いますねそのマクロ的以外のところを考えた時に、その国が好きか、そこの国にいる人たちが好き、文化、食べ物、そこを全部ひっくるめてというか、そこに長いこと自分が入れるかどうかっていうのも結構大事なんじゃないかなとは思いますね。
後藤さん「そうですねだからそういう観点で言うと、アメリカと州によって全然違うと思うんですけど、サンフランシスコは僕は本当に好きだなと思っていて、サンフランシスコって何かザ・アメリカっていうのとちょっと違うと思うんですよね。」
—確かにそう言われるとそうかもしれないな。
後藤さん「典型的なアメリカって 東海岸だったりとかすると思うんですよ ニューヨークなんか もうちょっとこう 東海岸で、じゃあもっと 田舎の方とか行ったら、多分 もういわゆる トラディショナルなアメリカって感じるんですよ なんですけどサンフランシスコですごい思うのはやっぱり 世界中から人が来ていて、 そこで競争があるっていうところが やっぱりここまで 競争が激しくて、要は 世界中で何かこう...良い 力を持った人たちが集まってる、 そういう、 何て言うんですかね、世界戦みたいな イメージがあるんですよ 世界戦というのは 線の方ではなくて 戦いの方ですけど、 そこで世界中のトップタレントと いろいろ競って 勝ち上がっていく っていうことができる環境って 他にはないなと思っていて そういう意味では すごく居心地がいいというか、 ここで頑張ろうっていう気持ちになりますね」
—ありがとうございます。後藤さんは結構日本のスタートアップも経験されてるし、今まさに自分のスタートアップをアメリカでチャレンジ中だと思うんですけども、おそらく日本と米国の違いというか、全部色々と比較できるんじゃないかなというふうにちょっと思っていましてもちろんそのカルチャーギャップももちろん当たり前ですけど、まぁ色々あるとは思いますけど、後藤さん的に日本と米国のスタートアップカルチャーの大きな違いってもちろん色々あると思うんですけども、いくつか挙げるとすると、どういう時にここがやっぱ大きく違うなって感じるところってどういうところだったりするんですか?
後藤さん「そうですね 何か カルチャーが違うな ということは もちろんあるんですけど、すごく思うのは、 なんでその 文化が違うのかっていうのは環境の違いだと すごく思いますね 端的に言うと、最新技術を使った 事業って、ちょっと前で言ったらWeb.も そうですし、今だったらAIもそうだったんですけど、 技術が結構 黎明期のタイミングでも 割と事業化ができるっていうのが サンフランシスコの 特徴だなって思ってますね これ、なんでできるかってときに、 気質とかそういう話も あるんですけど、合理的に考えていくと そうなるっていうところがあって、もう少し、 例えば、 今3DのAIって めちゃめちゃクオリティ 的には全然低いんですよ けど、もう 競合が何個も出てきていて、 ものによっては億くらい調達してる所があるんですね なんでできるかっていうと、 サンフランシスコベースで 物事を作っていて、グローバルに プロダクトベースで広げていくと、ギリギリ 事業化できるくらいの パイを世界中から かき集めることができるんですよね で、 そうなってくると、じゃあ 初期のプロダクトっていうのは当然、 まあ例えば BtoC寄りだったり とか、もしくはそのままBS寄りの事業にして そういうものでも少額でも トラクション作れるようにしていって で物事を進めていきます そうすると投資家サイドも そこの初期のトラクションを見て 投資をするし、事業としても SMB向けとか BtoC寄りの形で 物を作って広げるみたいなところが 広がっていて、で、じゃあそういう 新技術を作って広げていくってのが 成り立つ環境があるので、 そういうのやりたい人が多い ちょっと順番はどれが先とかわかんないんですけど、 これができるっていうのが USの特徴かなと 日本の場合は おんなじような新技術の領域をやろうとしたら エンプラ向け以外だと ほぼできないんじゃないかなと思っていて もちろんBtoCで SMB向けでグローバル上がってくる ケースもあると思うんですけど、新技術を やりたいですと そうなった時に、日本国内だけを ターゲットにすると当然 BtoCでもSMBでも数が足りないと じゃあ行ってマネタイズしていこうって なったら、当然エンタープライズになるんで なんでエンタープライズが 日本のスタートアップに 案件を発注するかっていうと、 エンタープライズが お金を出す先が、 USの場合はMAとかになるんですけど、日本の場合は チームを買って作るってことをしなくて 内省したがるので、DXって形で、代わりに 作ってくれる人、サポートしてくれるところを 探すとなると、DX案件として スタートアップの発注がくると なので、 そこからお金を集めようって なので エコシステムでの差だったりとか、アクセスできる マーケットの特性の 違いによってどういう サービスがどのタイミングでできるかって 全然違うので、まあ、 だからイケてるとされる事業とか、 そこで変わって結果として そういうカルチャーの 違いだったりとか、じゃ 投資家の志向性だったりとかって 変わってきて だからアメリカ人は すごいリスクテイカーだから とかってことではなくて、全部 僕が最初思ったんですよ アメリカの投資家って めちゃめちゃ ガバガバお金出すんじゃないかなって そんなことなくて 当たり前なんですけど ちゃんと合理的に 考えていくと、そっちになんか 最適化されていくんですよね なので そういう前提の差でしかないんですけど、その前提が 今言ったような、 じゃあ大手企業っていう お金持っているところがどこに お金を出すかの差もあるし、 アクセスできる マーケットの規模の差もあるし、 じゃあその中で どうやってマネタイズしていくかの 差があるんで、結果 こういうところがイケてると 決まるけど、もうそこの違いでしかないと思います。」
—ありがとうございます で、 あと気になるのは、 おそらく日本でもGaudiy結構大きく資金 調達してたニュースとか見たことありますし、 もちろん自分のスタートアップにも その資金調達の経験があると思うんですけど、その 資金調達の観点で 日本とアメリカの違いって どういうところがあるのかっていう ところと、あと その投資家目線で、ここ やっぱアメリカと米国の 大きな違いというか、 どういう点だったりするんですか?
後藤さん「そうですね 最終的には 投資の意思決定っていうのはそんなに変わらない 気もしてるんですけど、まず一番最初に 違うのは、 そもそも投資家に アクセスするための 準備っていう ところが、USの場合は 圧倒的に必要だっていう ところはそう感じます 日本の場合は、いわゆる プレシードから シードラウンドっていうところに関して、 少なくとも投資担当と 会話ができない っていうことはないと思うんですよ まあ一応会話はちゃんとできて すごい初期的なデューデリまでは たどり着けるみたいなことは 当たり前だと思うんですよね 日本であれば スタートアップも少ないし、 なんですけど、USだったらやっぱり スタートアップやりたい 数がめちゃめちゃ多いので、 やっぱりスクリーニングを まず抜けないといけない じゃあどうやって スクリーニング抜けるかってステップは 個手前に入ってくるんですね それがいわゆるエンジェルだったり とか、アクセラプログラムだったりとか、 もしくはリファラルで VCにアクセスしたりとか、何か そこがあって、それを超えなきゃいけない そのためにはかなり 短時間で、 めちゃめちゃ興味を持たせるための 材料を、それが もちろん人間関係かもしれないし、ピッチでも それもぱっと 興味持ってもらえるような USのVCでいったら、例えば ひと月で件ぐらいのピッチで デューデリしています みたいな形で でかいとこだともっとあるんですけど、 その中で、じゃあもう 本当に数秒しか目を通されない 中で目立つとか、何かそういう ちゃんと話を進める前の そうですね、そこの競争があるんですね あとはそうですね、これも 最終的な投資判断で もちろん見ると思うんですけど、日本よりかは いわゆる Why Nowとか、何か ストーリーとか何か ビジョンとか、そこは 聞かれないです っていうのは、 これは多分ですけど、 それは語る人が 多いんじゃないかなと思ってですね 一方でものを ちゃんと作れる人っていうのが 少ないってことなんじゃないかなと思うんですけど、 スタートアップやる人が少なくて、 本当にこの人 継続するんだとか、か、 本当にスタートアップやれんの?みたいな 確認が入ってくると思うんです 珍しいじゃないですか ある種、キャリア巣立って チャレンジするっていう発想に日本だとなる ただUSの場合だったらもう山ほどいて、みんな そういうやりたいって 本当にできるかどうかって、 何か表現力とかじゃなく 続けるかどうかじゃなくって、 本当にやったかどうかを 見るって感じで、スクリーニングの聞き方が 違うと思います。」
—なるほど ある意味、後藤さんは もちろん、アメリカでいろいろ やっぱりベースで行ってるわけですし、 もう、いきなり飛び込んで 何もコネクションがない中 やってたと思うんですけども どういう工夫をされてたんですか もちろん先ほど 香港のアクセラ っていうのも 中には出てきましたし、 今に至るまでに どういうことをやってたんですか いろんな コネクションとか、 いろんな方々につながるためには、 そこはいろんな努力と 工夫をやられていたと思うんですけども、 参考までに 教えていただければなと思います。
後藤さん「そうですね まあ僕の場合は本当に何か周りに 助けてもらってるっていうのが 本当に正直なところで、 やっぱり日本のいわゆる USの日本のコミュニティーの紹介だったりとか、 あとは ジェトロさんが いわゆるアクセラのサポートをしてるんですけど、まあ もう本当に そのつじゃないですかね 僕の場合は もちろん自分でも イベント行って、その例えばAIのイベント 登壇しましたみたいなのは、僕が 要はネットワークイベントに行って、 オーガナイザーと話して みたいなところだったんですけど、 ゲーム関係の人と繋がったりとか、ある種 ユーザー公募になるような人とか 繋がりとか、最初はもうそういう コミュニティーからの紹介だったりとかなので まずはそこ からって感じだと思います それ以降に関しては、僕の場合は ちゃんと物を作って物を見てもらって 興味を持ってもらうことに シフトしたので、物作りを 頑張ったっていう感じで、何かこう、 何て言うんですか、めちゃめちゃ何か 営業が得意とかそういうタイプでもないんで、 特殊な努力をしたかっていうと そうではないとは思ってるんです けど、本当に助けられたりとか 面白いものを作って話してもらえるようにしたりとか っていう感じですね 僕の場合は。」
—ちなみにアメリカのアクセラとかって結構その選ばれるためには結構色々ハードルが高そうだなって勝手に感じてるんですけどもやっぱり例えばアイデアベースとかあって、だからまだプロトタイプがない、ベータ版もまだ出せてない状況において、アクセラに参加するのって結構有効的なんですか?
後藤さん「参加できたら めっちゃ有効だと思うんですけど、やっぱ 参加の難易度はすごい 高いなって思いますね 高いですよね、きっとね なんか 本当に何も持ってない人が 何か無作為に応募して 当たるということは ほぼないんじゃないかなと思うんですよね めちゃめちゃいるし、何か これが日本の人が心折れ易くなる理由だと思うんですけど 日本だったら起業しますって 言っても、何か ちゃんと扱ってくれてる気がするんですよね なんですけど、 こっちだと山ほどいるので、 そういうところで めちゃくちゃ扱いは悪いわけですね 特に こっちでバックグラウンドがない 移民で、まだよく分かんない ファウンダーやりたいですっていう人ってのは もうなんだったら現地のイベントにしか 参加できないことも多いんで サンフランシスコでもすごい 最近Lumaっていうとこで イベントを開いたことがあって 日本でも ああいうところとか当然から入るわけなんで、 本当に のプロフィールとか載せるわけなんですね 多分ちゃんとした繋がりとかないと、もう 足切りなる...もう参加すらできない そういう感じなんで ちゃんと抜きんでる戦略は考えないといけないと思います。」
—ちなみにアメリカのアクセラとかって、もちろんアクセラによってはいろんなその選考基準はいろいろあるとは思うんですけども、その共通するとこってどういうところを見たりしてるんですかね
後藤さん「やっぱりプロダクト作れるかはすごく見てると思うんですよね。」
—ちゃんとそのチームが作れるかどうか。
後藤さん「そうですね ポテンシャルで評価する ケースっていうのは 本当に少ないと思うし、ポテンシャル 評価得たかったら スタンフォード出てみるとか、 そういう話だと思うんですよね GAFA 日本人がこっち行った時にポテンシャルで 評価される US視点でのポテンシャル 評価になり得る項目が ほぼないと思うんで ってなってくると、 実績持っていくしかないですね もしくは作れる でも作れるチーム だったら、じゃあ作れるもの 持ってトラクション持ってきてね ってなってると思うんで 大体が ってなると 結局アイディアベースで 勝負するってのは 難しいんじゃないかなって思います。」
—なるほど。もしアクセラに応募するなら自分達で作れる力があるかっていうことと、トラクションを作れるかどうかそのチームを構成するのが結構最低限重要かもしれないっていうことですね。
後藤さん「そうですね 多分メンバーを日本で 集めてこっち来ましたって なった時に、じゃあ USでトラクションとれる保証になるかっていうと なること少ないと思うんですよね ほとんどケースでは なのでプロダクトを ちゃんと作って、 それで数字を伸ばすっていうところの重要性は 日本より高い気がしますね。」
—うん確かに結構割とトラクション気にするような感じがしますねやっぱ結構最重要視するっていうかトラクションがなかったら、そのスタートアップがSurviveできないので、やっぱそれは割と結構アメリカの投資家はすごく見てるような感じしますね。
後藤さん「そうっすね 簡単に 例えば ウェイトリストの数とか じゃコールドメール バーッて送ってリード取るとか、 そういうことは 日本よりはやりやすいと思うんで まあ結局そういうトラクションの数が 集めやすいプロダクトが チャレンジしやすいですよね なので そういう方向に寄るっていうのも 側面はあると思うんですけど、 そういうのを集めるぐらい 全然できるでしょ っていう感じなので、持っていかないと 大変だなって感じますね。」
—ありがとうございます ちなみに日本では スタートアップ カ年計画みたいなもの って、結構今政府とかも 頑張って掲げているんですけども、 その日本の スタートアップエコシステムが 後藤さんの視点で もっと盛り上げるためには どうしたらいいのかっていうのと、あと ユニコーンの数を増やすっていう 多分狙いもあると思うので、ユニコーンの数を増やすには どうしたらいいと思いますか?
後藤さん「そうですね まぁでも日本の っていうところで関してで言うと、 多分、今進んでると思うんすけど、全体的に 流動性を上げることだと思うんですよね これはいわゆる 最近もこういう話が占めてると思うんですけど M&AのEXITって もう個流動性あると思いますし、 いわゆる チームメンバーのSOだったりとかじゃ、 セカンダリーの流動性とかもそうですよね 日本の場合だと ちょっと詳しい数はわからないですけど、結局、 IPOをしていかないと いけない IPOをしていくってなったら どうでしょう 5年とか7年とか、 それぐらいはかかってると思うんですよ 長かったら年とかいってるのかわかんないですけど、 で、てなってくると スタートアップにジョインするとか、 そういう活動するってなんか凄い、こう、 なんていうんですかね、最初から入って 最後までめちゃくちゃ人生をかけて コミットするのがすごく ハードル高いものになって、ファウンダーは それでいいと思うんですけど、チームの方ですよね 何かメンバーだったりとか、そこを もっと採用しやすかったりとか、 良い人に入ってもらいやすかったりとか、 まあそこで じゃあそういう人が入ったとして、そこから得られる 期待収益というのを考える には、EXIT先も そうですし、もしくは持っているもの っていうのはちゃんと セカンダリーで 個人としてもEXITができる そこがないと 難しいなと思いました というのは、結局 今のメンバーにいてくれてる人とか、もう 何ていうんですかね 元Facebookの方とか、もう 全然気楽に入れるわけですよ ある意味 スタートアップなんですけど 日本だったらどうなんでしょう 結構こういう人を採用するのって 何だろう めちゃめちゃ 知り合いでとか、何か そこぐらいまでいかないと 元GAFAで起業経験ありますみたいな人が チームに入ることって無いと思うんですけど、なんか 自分の感覚では驚くぐらい 拍子抜けぐらいの関係性で入ってもらったりとか、 それは何か そこのいろんなチームを行き来してた ハードル低さがあると思っているので、流動性が 全体的に必要なんだろうなと スタートアップとしても個人としても必要だなと思います。」
—なるほど、ありがとうございます確かに最近いろんな整備され始めているなっていうのも、結構いろんな動きを見ていてすごく感じるので、結構いい感じに物事が進んでいるんじゃないかなというふうにも思いますし、あと、エンジェル税制ももちろんそうですしねこのエンジェル投資家は、日本のエンジェル投資家がもっときっとこれでよりエンジェル投資しやすい感じにもなるんじゃないかなと思いますしそうですね少しずつではあるけども、本当にいい流れが来てるなっていう感じがすごくしますね気づいたらもう本当に結構長くなってしまっているんですけども、そのアセットハブとして今後の展開っていうのは、もし現時点で考えていることがあれば教えてください。
後藤さん「そうですね 僕らはやっていることっていうのは 本当にある種 何ですかね AIを使って コンテンツを作るっていうことは、 まあ今までだったら 何て言うんですかね、例えば ゲームの中で言っても、じゃあ家庭用 ゲームができて、ドラクエ、FFとかっていうIPができて モバイルゲームが出てきて、 パズドラだったりとか、何か 今新しいゲームジャンルとか、人気のIPとか... 今ってデバイスの 違いがないので、デバイスに合わせてコンテンツ作り、 ゲームチェンジのタイミングでIP生まれて、 今もうそれがないと思うんで 次は AIの制約に合わせて 物事を作っていく そういう戦い方のままで、次のビッグIP 生まれてくると思うんですよ なので 僕らはそういう 新しいIPが作られるような メディアだったり 領域ってのを作っていきたいし、 その中でまあ次のディズニーの デカいIPを作る人が クリエイティブの人たちが一番好きだって 言われるような形になりたいんですね なので、そういうような 環境も、まあ次のIP 作りってところも、まあ何か 実現をしていきたいっていうのが これって僕が思うのは、日本ってめちゃめちゃ IP大国なんですけど、これは 漫画があるからだと思ってるんですよね つまり、個人とか少人数で たくさんのメディアを量産して 評価をされるマーケットがあるっていうのは 日本しかなかった 漫画しかなかった 海外だったら 映画とかゲームとか そうですね だからIPが少ない でもこれがAIベースになってくることによって、少人数で ゲームが作れるとかになって くると、日本の漫画みたいなものに インディーゲームとか っていう風になると思うんですよ なので 日本的な感覚での IPが作られる土壌、敷居も 低くて、みんながチャレンジして 新しいものになる。そういう領域っていうのを 領域とか考え方っていうのを アメリカでも実現したい それをAIで やっていきたいなと思っているので、これから そういうトレンドを アメリカで作っていきたいなと思ってます。」
—ありがとうございます非常に素晴らしいですね全力で応援しますちなみに後藤さんのこともっと話聞きたいとか、ちょっと連絡したいっていう時ってどういうところでアプローチするのが一番いいんですか?
後藤さん「そうですね なんか TwitterとかでちょっとDMくれたら 見るかもしれない 見ます。」
—確かにそうですよね結構お忙しいですし、そうなのでちょっとTwitterのXのアカウント名とかもちょっと概要欄とかにも入れておきたいなと思ってますので、もし後藤さんの話を聞きたいとか、そのAI領域についてちょっと何か質問したいとか、米国のことをもっと知りたいというようになったら、ぜひぜひ気軽に提案してくださいもう最後になりますが、最後に一言海外にもしチャレンジしたい若者だったり、起業家がいたら、もし何か一言あればお願いします。
後藤さん「そうですね ある種、アメリカで チャレンジするっていうのは、 スタートアップ的にはめちゃめちゃ強いと つまり言語とか色んなこと 壁感じるかもしれないですけど、強い事業を作ろうとか でかい事業を作ろうとしたらアメリカの方が 圧倒的に簡単だなって思ってるんですよ なので とりあえずチャレンジしたい人は ぜひこっちに来て、一緒に ちょっとチャレンジできると 面白いんじゃないかなと思うんで、皆さん アメリカ来てください、よろしくお願いします。」
—ありがとうございます RiZiN Podcastを観ていただき、ありがとうございます もし周りに 海外に興味がある、海外に チャレンジしたいという方がいましたら、ぜひ このポッドキャストをSpotify、Apple、 Google Podcastで 聴けるので シェアしていただけますと嬉しいです ついでにフォローもしていただけると モチベーションになるのでお願いします では、また次のエピソードでお会いしましょう ご視聴ありがとうございました。